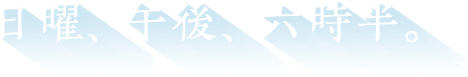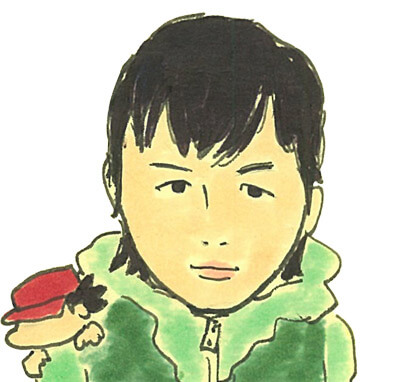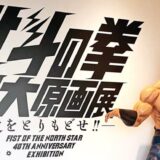人間の底すらない悪意を描いた作品。
ただ、ドラマティックな展開はなし。
そのため、映画的なカタルシスを期待して観に行くと肩透かしを食らうかと思います。

こういった類(たぐい)の映画ではない
本作品は見る側の想像力/読解力が多分に必要、かつ、ホロコーストで何が行われたか一定の知識がないと“かなり“退屈に感じるかと。
だって、作りとしては“ほぼ“Vlogですからね。しかもYouTuberみたく視聴者に語りかけることはなし。
ただただ、ある家族の日常を定点観測するだけ。
でも、ホロコーストへの造詣が深い人が見れば、無関心こそ恐怖/無関心こそ最大の罪であることを心底実感できる。そんな作品。
個人的に見ててキツかったのは、以下2つ。
- エンドロール
- 夫の転勤が決まった時に起きる夫婦喧嘩
エンドロールは、人の悲鳴や叫びとも知れぬものが幾重にも折り重なった不協和音がずーっと鳴り響くという演出。
なので、劇中では、遠巻きに聞こえてた音がエンドロールではダイレクトに浴びせられます。人の怨嗟が渦巻く声を。
—
夫婦喧嘩は、妻の言い分がきつく、終始「お前は何を言ってるんだ」状態。
特に諭すような感じで「家族は一緒に居なきゃ…」と言うシーンは、あまりのグロさ・おぞましさに心底 胸糞が悪くなりました。
だって、家の隣の収容所では、家族をバラバラに引き裂いている訳です。それも比喩(ひゆ)ではなく文字通りの意味で。

アンネ・フランクの家(2010年撮影)
その上で「家族は一緒にいなきゃ…」と”のたまう”訳ですよ。
しかも(隣で行なわれていることに対し)無自覚でなく明らかに自覚的な上で。
でも、彼女らにとってユダヤ人が“どうなろうと“どうでもいいんですよね。なぜなら関心領域「外」だから。

家族以外は黒く塗りつぶされている
この映画、いろんな捉え方ができるかと思います。
特に今現在、ウクライナやロシア、ガザでは戦争が起こり膨大な犠牲が出ている訳で。
なので決して昔の話ではなく、現在と地続きの話なんですよね。
それを“揶揄(やゆ)“する演出が、ピンホールを通して過去と現在をリンクさせるというもの。
ピンホール(カメラ)の原理って、穴を通した先も同じモノが投影されるわけで。
ラスト近く、ピンホールの先にいるヘス(アウシュヴッツの所長)が、”こちら”を直視してるのは、そういうこと。
つまり、ヘスと現代にいる我々が同じ穴のムジナであることを指してるわけです。
“正義の対義語はもう一方の正義“というのを痛感させられる映画でした。
そんな感じで。終わり。